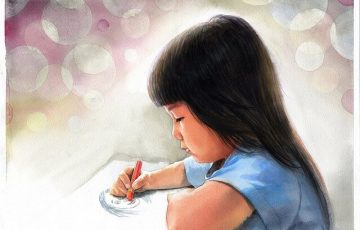最近、子供のしつけについてのニュースをよくみかけますよね。
最近の子はしつけがなっていない。とよく言われています。
しつけ、虐待、体罰・・似ているようで全然意味が違う、でも説明するとなると難しい言葉って、意外とたくさんあります。
今回は『躾』について考えてみたいと思います。
『躾』という漢字の語源
漢字といえば中国から伝わったと考えるかたが多いと思います。しかし『躾』という漢字は「国字」や「和製漢字」と呼ばれていて、日本で考えられた漢字です。
他にも峠、畑、凪、働、笹なども「国字」だと言われています。
『躾』という漢字を分解してみると「身」と「美」という字に分けられます。
「身」は女性が身ごもった姿を表し、「美」は「羊」と「大」で、肥えた羊のように立派な姿を表しています。
『躾』は、『身を美しくする、美しく保つ』と解釈できますね。外見ではなく、行動や仕草の中に垣間見えるその人の本質のことを指すといわれています。
なぜ『しつけ』と読むのか
『躾』という漢字はなぜ『しつけ』となったのでしょうか?
一般的に言われているのは仏教用語で『習慣性』を意味する『じっけ(習気)』からきていると言われています。
その『じっけ』が一般に広まる過程で『しつけ』に変化し、『作りつける』意味の動詞である『しつける』が名詞化して『しつけ』と混合されてできたといわれています。
着物などを作る際、仕立てが狂わないように仮留めする糸を『しつけ糸』と言いますが、これをしないと着物が正確に作れないことから、人間的にほころびがでないように教育するという意味をもつともいわれています。
漢字や読み方からみる『しつけ』の意味
しつけは、先ほど『しつけ糸』からきているとお話ししましたが、しつけ糸は着物が完成するにつれて外さなければなりません。
これは、こどもに対するしつけでも同じことが言えます。
こどもはいずれ大人になり、親離れをして独り立ちしていきますよね。親も子離れをしなければなりません。その時にある程度一人でできるように、困らないようにしてあげることが本当の『しつけ』ではないでしょうか。
そのためにも、親がお手本とならなければなりません。親の背中を見て子は育つといいますが、言葉で伝えることも大事ですが、行動で示すことがしつけの第一歩です。
心配になる気持ちもわかりますが、将来のために過保護に育てるよりも、ある程度の失敗を経験させることも大事なのではないでしょうか。その経験を活かすためのサポートをできたらいいと思います。