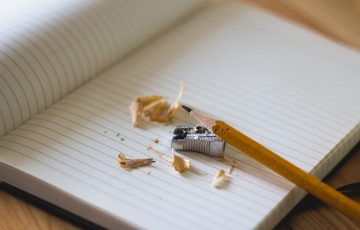最近メディアでもよく耳にするようになった『発達障害』。
この20年あまりで7倍以上にも増加したと言われています。
文部科学省が2012年に実施した全国調査の結果では、15人に1人のお子さんが何らかの発達障害傾向を持っているとのことです。
(出典:文部科学省 通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について 2012年)
けっして珍しくない発達障害。
かく言う私も、現在発達障害を持つ子どもを育てています。
歳の差三兄妹の一番上、10歳の長男がそれに当たります。
発達障害には自閉症、アスペルガー症候群など様々なものがあり、症状も一人一人違ってきます。
(出典:LITALICO発達ナビ 発達障害とは?発達障害の分類・症状・特徴・診断方法はどのようなもの?)
今回はその中でも軽度自閉症の長男を育ててきて私が感じた苦悩や、その先で見つけた喜びについてお話しします。
発達障害に馴染みのない方にとっても、一般的な子育てとの違いを知るきっかけになればと思います。
周りのママたちと子育ての悩みが共有できない
子育てをしていると成長と共に様々な悩みが出てきますよね。
「うちの子やんちゃで目が離さないの」
「おしゃべりが早くて相手をするのが大変」
「自分から勉強をしなくて困っちゃう」
「お友だちとまた喧嘩してきたの」
年齢相応の子育ての悩み。
発達障害の長男を育てる私にはとても遠い世界のものでした。
障害の有無を問わず、悩みながら子育てをすることはどの家庭も共通しています。
その悩みに軽い・重いは無いと思っています。
しかし、年齢相応の悩みがわからず共感しあえないということはとても孤独なものでした。
自分の悩みを吐き出せば返ってくる言葉は
「気にしすぎじゃない?」
自分が年齢相応の悩みを理解できないのと同様に、周りも発達障害特有の悩みを理解することが難しかったのだと思います。
年齢相応の発達をしている長女(8歳)・次女(0歳)を育てている今、理解できないお互いの気持ちがようやくわかりました。
身内なのに理解されない悲しみ

わが子が誕生した時、離れて暮らす祖父母も大変喜んでくれました。
この先自分たち両親だけでなく祖父母にも愛されて、すくすく育って行くのだろうと思っていました。
長男の障害がわかるまでは。
徐々に周りの子たちとの違いが目立ちだし障害があることがわかり、とても落胆をされたことを覚えています。
簡単に受け入れられることではないと思います。
私自身もどうすればいいかわかりませんでした。
それでも血の繋がった身内に否定されることは、とても堪えられるものではありませんでした。
このことがきっかけになり、身内でありながら距離を置くことになってしまいました。
外出先での心無い言葉に胸を痛める
環境の変化が苦手な長男は公共交通機関、特に長時間乗り続ける電車がとても苦痛でした。
今でこそ落ち着いていられますが、幼児期は常にパニックとの隣り合わせでした。
ある日おばあちゃんの家に行くために電車に乗りました。
時間は比較的乗客の少ないお昼間。
天気も良く外の景色を眺めている長男はいつもに比べてとても落ち着いているように見えました。
安心していた矢先、交通トラブルで電車が急停車しました。
流れる景色が止まったことで落ち着きをなくす長男。
周りのざわめく声に彼のパニックのスイッチが入りました。
すぐに運行は再開しましたが、一度入ったスイッチは切れることなく大声で泣き出しました。
抱っこをしたりおもちゃで気を逸らすも全く目に入りません。
こうなったら落ち着くのを待つしかなく、私は泣いて暴れる長男の体をぎゅっと抱きしめ続けました。
しかし他の乗客にとっては迷惑でしかないのですよね。
「うるさい、さっさと泣き止ませてくれ」
「母親のくせに泣き止ませられないのか」
「迷惑だと思っているなら電車を降りてくれ」
直接的だったり間接的だったり、様々な声が届いてきました。
特急電車の次の停車駅までの時間が、いつも以上に長く感じました。
しばらくして次の駅に到着し、私は逃げるように電車から飛び出しました。
地獄のような時間を過ごした電車を見送ってふと気付くと、同じ電車に乗り合わせていたと思われるお婆さんが私にハンカチを差し出して立っていました。
そこでやっと気が付きました。
長男以上に自分の顔が涙でぐちゃぐちゃになっていたのです。
思いもよらない優しさに触れて決意
おかしな話ですが、最初はそのハンカチの意味がわかりませんでした。
長男を連れていて声をかけられる時はネガティブなことばかりだったため、長男が車内で泣き叫んでいたことを咎められるものだと思っていたのです。
しかしハンカチと共に掛けられた言葉は、とても温かく優しいものでした。
発達障害は目に見えない障害です。
そのため周囲からの理解が得にくく、誤解され傷つくことが日常になっていました。
無意識に人目を避けるようになり、次第に人との関わりが減り、人の優しさに触れる機会がなくなっていました。
このことがあって今まで目に入らなかった周囲の優しさを知ることができました。
そして発達障害の長男と共に前向きに生きていく決意をしたのです。
療育を始めてで広がった世界

それからは長男のためになることを模索しました。
同時に悩んで先延ばしにしていた療育施設への入所を決意しました。
施設には発達に不安を抱える親子が大勢通っており、自分と同じような境遇のママたちと出会うことができました。
ここでようやく孤独を感じず子育てができるようになりました。
また長男を通して障害や福祉を学び、今まで自分の知らなかった新しい世界を知ることができました。
障害があっても社会で立派に働く人たちがいることを知りました。
障害があるからこそ発揮される力がたくさんあることを知りました。
障害がわかり真っ暗になっていた未来が少しずつ色づいてきました。
幼児期に施設でたくさんのことを学び、親子共に大きく成長ができました。
そして小学生になるためのしっかりとした土台作りができました。
早期療育をして良かったと、今改めて思います。
長男を通して深まった家族の絆
長男が療育を初めてから、夫婦で子どもたちのことについて相談する機会が増えました。
近い未来のことだけでなく、成人したその先のことまで、何度も何度も話しました。
そのおかげで、今まで気が付くことができなかった長男の良いところもたくさん見つかりました。
人より幼い、けれどとても素直。
人より繊細、けれどとても心優しい。
人より不器用、けれどとても真面目で一生懸命。
そんな長所をこの先活かせるよう、家族で支えていきたいと思えるようになりました。
悲しいことに、子どもの障害がわかってうまくいかなくなった夫婦も少なくありません。
背負うには重すぎる問題、気持ちは理解できます。
しかし、どうか後ろを向かず明るい未来の話を夫婦でしてもらいたいです。
想像もつかないようなずっと先の話を、「こんな大人になってほしい」という夢を、たくさん話してほしいです。
そうしているうちに子どもはどんどん成長して、遠いと思っていた未来が気が付けば目の前に見えるようになります。
思っている以上に時間が経つのは早いですよ。
無理に受け入れようとしなくていいのです
「障害は個性と思えばいい」という言葉をよく聞きますが、日々苦悩しながら育てている身としてはそんな簡単に思えることではないと感じています。
愛しているがゆえに、長くわが子の障害を受け入れられず苦しむ方も多くいらっしゃいます。
無理に受け入れようとしなくてもいいと私は思います。
その子の性格に合わせて、その子の時間の流れに合わせて、進んだり戻ったりを繰り返してください。
そうして気が付いた時にはきっと、以前よりもほんの少し先に進んでいることと思います。
そして可能であれば心を閉ざさず外の世界を見て、周囲の優しさに触れてほしいです。
まだまだ続く子育て生活。
これからも日々迷いながら親子共に成長していきたいと思います。