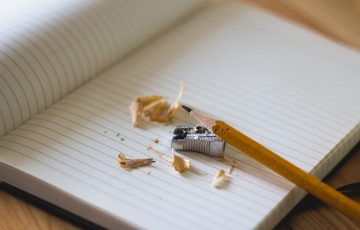子育て真っ最中の皆さんに質問です。
いつが子育て疲れのピークだと思いますか?
「今が一番しんどい!」
「○歳の頃が一番しんどかった!」
様々な意見が出てくるかと思います。
私自身現在10歳・8歳・0歳の子育て真っ最中ですが、子どもによって様々なタイミングで
「もうしんどい!限界!」
と思いながらなんとか子育てを続けています。
しかし、実際はいつが子育て疲れのピークなのでしょうね?
今回は3児の母である私が10歳までの子育てで疲れを感じた時期をランキング形式で紹介しますね。
【5位】10歳
まさに今です!
子育てって年々楽になっていくイメージがありますよね。
実際、波はあれど体力的な疲れは年々感じなくなってきました。
さすがに叫びながら追いかける必要はありませんしね。
目を離しても、それなりに自分で考えて行動ができるようになる年齢です。
ただ手や口を出す頻度が減った分、忍耐力が必要になるのがこの時期です。
小さい頃は子ども同士のトラブルに親が干渉することができましたが、10歳にもなるとそうはいきません。
近年学校でのいじめ問題がニュースで取り上げられることが増えましたよね。
小さい頃は「子どものいじわる」だったものが「深刻ないじめ」に変わるのがちょうどこの時期なのです。
なぜ「深刻ないじめ」に変わるのかというと、この時期の子は子ども同士のトラブルがあっても大人の耳に入れないことが多いのです。
日常的に学校での様子を聞くも、小さい頃のように全てを話してくれなくなるのです。
「お父さんやお母さんに心配をかけたくない」
「トラブルがあったことを知られたくない」
そうした感情が芽生え、しつこく聞こうものなら余計に口を閉ざすことにもなるのです。
成長の証でもはあり嬉しく思いますが、同時に寂しさも感じるのですよね。
半分子どもで半分大人。
本人の気持ちを尊重しながら物事を伝えなければならず、親は忍耐力が必要になります。
頭ごなしに叱るわけでもなく、顔色をうかがって甘やかすわけでもなく、親子間で駆け引きをするのです。
「守る子育て」から「見守る子育て」に移行するこの時期、乳幼児期とは違った大変さを感じました。
【4位】3~4歳(年少組)
4歳といえば幼稚園や保育園の年少組の年齢です。
今まで家庭で過ごしていた子が、この時期に初めて集団生活を送ることになる場合が多いですね。
わが家の第一子と第二子は幼稚園に通っていたため、この時期に初めて集団生活を知りました。
特に第一子の時は自分も初めてのことで、勝手がわからず毎日心配ばかりしていました。
初めての集団生活を送るにあたりよくあることが、子ども同士のケンカなのですよね。
この時期の子どもは小さなことですぐケンカになります。
物の取り合い、一番の争奪戦…言葉で気持ちが上手く伝えられないため叩いたり噛んだりしてお友だちを怪我させてしまうこともあります。
特に第一子は気持ちの切り替えが苦手で、お友だちを困らせることが頻繁になりました。
わが子に悪気がなかったのはわかりますが、相手のお友だちや親御さんに申し訳ない気持ちになり、トラブルが起こる度に謝る幼稚園生活一年目でした。
幸い周りのママたちに恵まれていたため皆さんわが子を温かく見守ってくれましたが、どれだけ言い聞かせても伝わらないわが子を前に途方に暮れることもしばしば。
この頃の子どもは個人差が大きく
「あの子はあんなにお利口なのにうちの子は…」
「あの子はあんなに活発なのにうちの子は…」
比較したくないのについついよその子とわが子を比べてしまうことが多いのが、この集団生活一年目でした。
初めてわが子を通して子ども社会と関わることで、わが子とだけ向き合っていた頃と違った大変さを感じました。
【3位】0歳3ヶ月

私は昨年第三子を出産し3回目の生後3ヶ月を経験しました。
3回経験しているからこそ言えるのですが、産後初めて子育ての限界を感じるのは産後すぐでも生後1ヶ月でも生後2ヶ月でもなく、この生後3ヶ月なのです。
生後3ヶ月というと、早い子だと首がすわりはじめ、深夜の授乳回数も少なくなってくる頃ですね。
それだけ聞けば
「少し楽になって可愛い時期じゃないの?」
と思われることでしょう。
しかし、子育てでは初めての余裕が初めての挫折につながるのです。
生後すぐは生活がガラリと変化し疲れを感じる余裕はありません。
産後1ヶ月から2ヶ月は里帰りから自宅に戻り新生活に慣れることに必死で、ここでも疲れを感じる余裕はありません。
そして産後3ヶ月。
ここで初めて我に返るのです。
「もう何日もまとまって眠っていなくてつらい!」
「鏡に写った自分の姿がボロボロで悲しい!」
「もっとパパも子育てに協力してほしい!」
ようやく人間らしい感情が戻ってくるのがこの時期なのですよね。
認識してしまえばもう感情大爆発です!
産後女性ホルモンが低下して乱れ始める時期でもあるため、私もイライラしてよく夫に八つ当たりをしてしまいました。
特に第一子の時は夫婦間で子育ての分担がうまくできておらず、家事も子育ても何でも自分一人でやろうとしていたのですよね。
「手伝ってほしい」
という言葉をうまく伝えることができませんでした。
当時夫も子どもが増えたことをまだ自覚できておらず、「女性は子どもを産んだ瞬間から自然と母親になれるもの」と思っており、父親が子育てに参加するという発想がなかったそうです。
そうしたすれ違いが起こると、楽しいはずの子育てが不満の塊になってしまうのです。
あやすと笑うようになった赤ちゃんをかわいいと感じる反面、中途半端な余裕によって『自分は子育てに疲れている』ということを自覚してしまうこの生後3ヶ月が、乳児期で一番大変さを感じる時期と言えるでしょう。
【2位】2歳
2歳といえば子どものイヤイヤ期に悩まされているママたちが多い時期ですよね。
わが子たちが2歳の頃もそれはそれは壮絶でした。
2歳といえばほとんどの子がしっかり歩けるようになっており、おしゃべりする言葉も急激に増える時期です。
大人の言っていることがわかりだし会話を楽しめるようになってきたとを嬉しく思う反面、なぜか些細なことで『この世の終わり』のように泣き叫び暴れることが増えるのがこの2歳。
それでは当時の彼らの『この世の終わり』スイッチをいくつか紹介します。
・一緒に寝ていたはずのぬいぐるみが起きたら足元に転がっていた時
・はいているオムツがお気に入りの絵柄ではなかったことに気がついた時
・頑張ってはいた靴下が左右逆だった時
・りんごジュースだと思って飲んだものがスポーツドリンクだった時
・母が5本指ソックスをはいた時
・運転中に右折した時
・バイキンマンによってアンパンマンの顔が歪まされた時
おそるべし2歳!
わが子たちが2歳の頃はこの謎ルールに振り回され、毎日ボロ雑巾のようになっていたことを覚えています。
こうした『世界の終わり』スイッチが入ったわが子の気持ちを受け止めながらも、少しずつ社会で生きていくためのルールを教えていかなければなりません。
死なせないため必死に追いかけたり、約12kgの暴れる体を抱えたり。
思い通りにならないことを教えるために、あえてわが子の望み通りにしないこともあります。
『世界の終わり』スイッチが入ったわが子が外で泣き叫ぶことで、虐待と間違えられることもしばしば。
この時期は毎日が戦いなのです。
このような理由から、幼児期最初の壁である2歳があらゆる面で疲れを感じる時期だと思います。
【1位】7歳
これは意外だと思われるでしょうが、1位はなんと7歳!
学年でいうと小学1年生の後半から2年生の時期です。
2年生って小学校にも慣れ出し、少しずつ親の手が離れるため
「やっと楽になったー!」
と解放された気持ちになるのですよね。
それだけ聞くと何が大変でどう疲れを感じるか想像がつかないでしょう。
私の周りのママたちがこの時期共通して口にする子育てワードがあります。
『魔の2年生』
魔の2歳児を超える魔の2年生。
この時期の子どもは親の手が離れたことで自由の楽しさを知ることになります。
ただ、まだ分別がついていないため『ほどほど』のところで止めることができません。
そのため親の知らないところで問題行動を起こす子が急増するのです。
実は『初めての万引き』なんかもこの時期にすることが多く、きちんと向き合わなければこの先も繰り返すことになってしまいます。
また、これまで問題なく育ってきた子でも精神が不安定になることが多く、「言えば言うほど反発する」などという悩みが出てくるのがこの7歳なのです。
親の手が離れてもいつでもつかめるようにしておかなければならないため、大変難しい時期なのですよね。
わが子たちは外で問題行動を起こすことはありませんでしたが、家庭内では親子でぶつかることが急増しました。
よくわからないけれどイライラしているわが子を見てこちらもイライラ。
親に対して初めて本気の暴言をぶつけてきたのがこの時期でした。
本気の親子喧嘩をしたりゆっくり話をする時間を作ったりして、今ではすっかり落ち着きました。
放ったらかしにしようと思えばできてしまいますが、後になって必ずしわ寄せが来ます。
そのためそれが嫌ならばとことん向き合う必要があるこの7歳の時期が、最も子育て疲れのピークになるのだろうと私は思います。
まとめ

子どもが成人するまでの期間、何度も疲れの波がやってきます。
乳児期には乳児期なりの。
幼児期には幼児期なりの。
学童期には学童期なりの。
思春期には思春期なりの。
それぞれ違った大変さがあり、どこが疲れのピークかは子どもの性格や家庭環境によっても変わってきます。
ただ、反対にどの時期も違った楽しさがあります。
子育てに行き詰まって疲れを感じた時は、先にあるそんな楽しさを想像してみてはいかがでしょうか?
そうして疲れのピークを脱した頃にはきっと、良いことも悪いこともひっくるめて大切な思い出になっていると思いますよ!